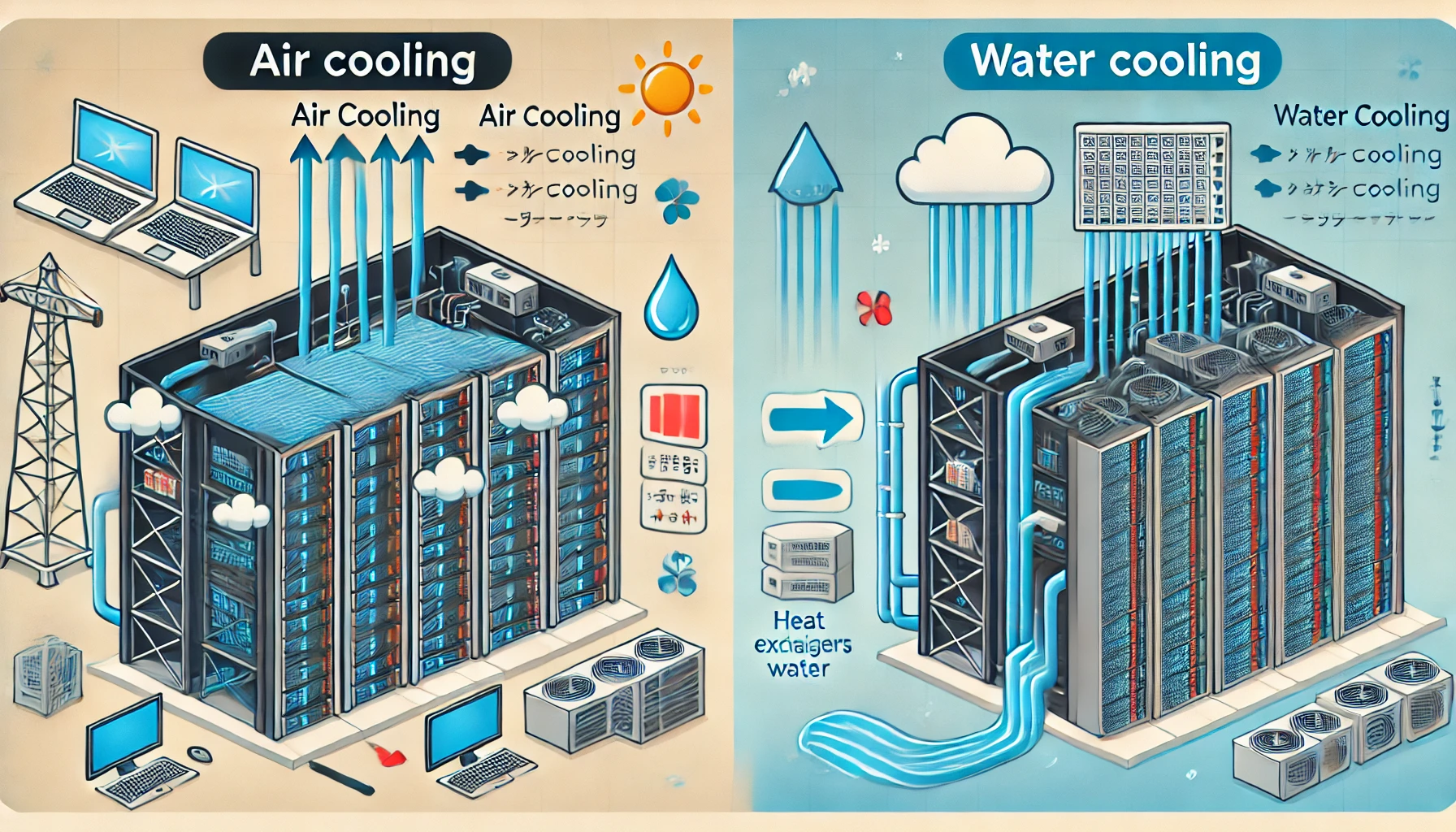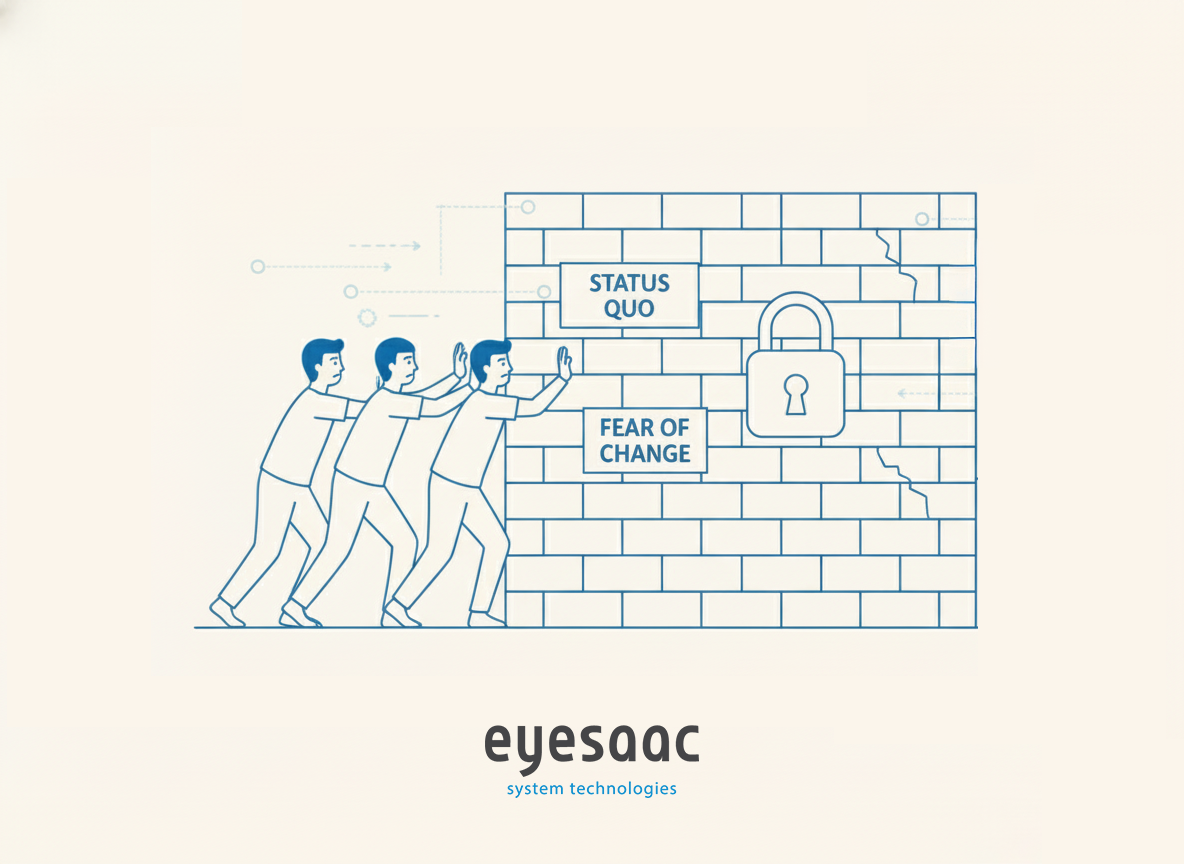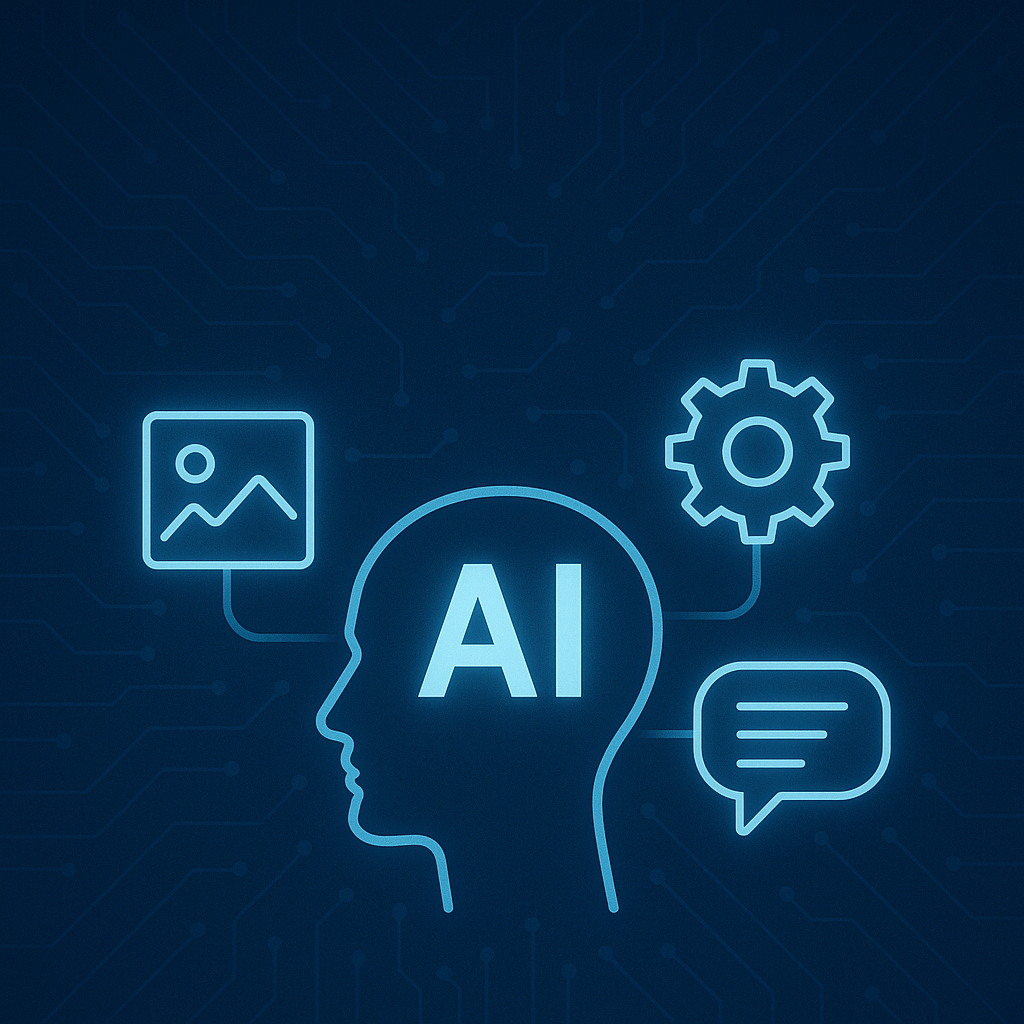― 経営レベルで導入を検討すべき理由 ―
「RPAの次はHyperAutomationだ」。
近年、ITベンダーやメディアでこの言葉を目にする機会が増えました。
しかし、実際の現場では「どこがRPAと違うのか」「なぜ経営層が関わるべきなのか」が十分に理解されていないケースが多く見られます。
Eyesaacはこの潮流を、“業務効率化の延長”ではなく、“経営構造を変えるテクノロジー”として捉えています。
その本質を理解しないまま導入すれば、再び「ツール導入で終わるDX」に陥る危険があります。
① RPAの限界 ― 「手順をなぞる自動化」
RPA(Robotic Process Automation)は、人の定型作業を置き換える技術として普及しました。
しかし、PwCの2024年レポートによると、導入企業の半数以上がROIの伸び悩みを感じていると報告されています。
理由は明確です。RPAは“ルール化された作業”しか扱えず、変化への対応力が乏しい。
環境が変わるたびにシナリオを修正し、管理コストが膨らむ構造です。
つまり、RPAは「業務を早くするツール」であっても、「業務を賢くする仕組み」ではないのです。
② HyperAutomationの本質 ― 「判断」を自動化する
Gartnerは、HyperAutomationを「AI・ML・NLPなど複数技術を統合し、意思決定を含む業務プロセス全体を自動化する概念」と定義しています。
このポイントは、“タスクの自動化”ではなく、“判断プロセスの自動化”にあります。
たとえば、請求処理なら「異常値の検出」までAIが行い、異常があれば自動で上長にエスカレーション。
マーケティングなら、キャンペーンの成果をAIが分析し、次の施策案を提示する。
RPAが「手を動かす自動化」なら、HyperAutomationは「考える自動化」です。
③ 経営視点での導入が不可欠な理由
HyperAutomationの導入で最も重要なのは、“どの判断を自動化すべきか”を決めることです。
これは業務部門ではなく、経営・事業責任者の意思決定領域に属します。
AIによって自動化される判断には、顧客体験・利益構造・リスク管理が直結するため、
経営戦略のリフレーミングが伴います。
Eyesaacは、この段階を「Automation Governance」と呼び、
“自動化を設計する組織”をどうつくるかを企業変革の中心課題として位置づけています。
④ HyperAutomationがもたらす構造変革
Accentureの2024年調査では、HyperAutomationを全社導入した企業の営業利益率は、平均で12〜18%改善しています。
その理由は単純なコスト削減ではなく、
- 意思決定のスピード向上
- 人的リソースの最適配置
- データに基づく統治(Data Governance)
といった“構造的な経営改善”が起きているためです。
自動化=効率化ではなく、経営の知能化。
これが、Eyesaacが定義するHyperAutomationの本質です。
まとめ ― Eyesaacの視点
HyperAutomationとは、AIを使って「経営の思考速度を上げる」取り組みです。
RPAの延長線ではなく、組織の意思決定フローを再設計する経営戦略。
技術導入を“コスト”ではなく“経営能力の拡張”と捉えた企業だけが、この波に乗ることができます。
Eyesaacは、AI・RPA・業務分析を統合した「判断の自動化アーキテクチャ」の構築を通じ、
企業が「速く」ではなく「賢く」動く未来を支援します。
引用元・参考文献
- Gartner (2024): The Future of HyperAutomation
- PwC (2024): Global RPA ROI Report
- Accenture (2024): Automation Intelligence Survey
- Eyesaac Consulting Insights (2023–2025)