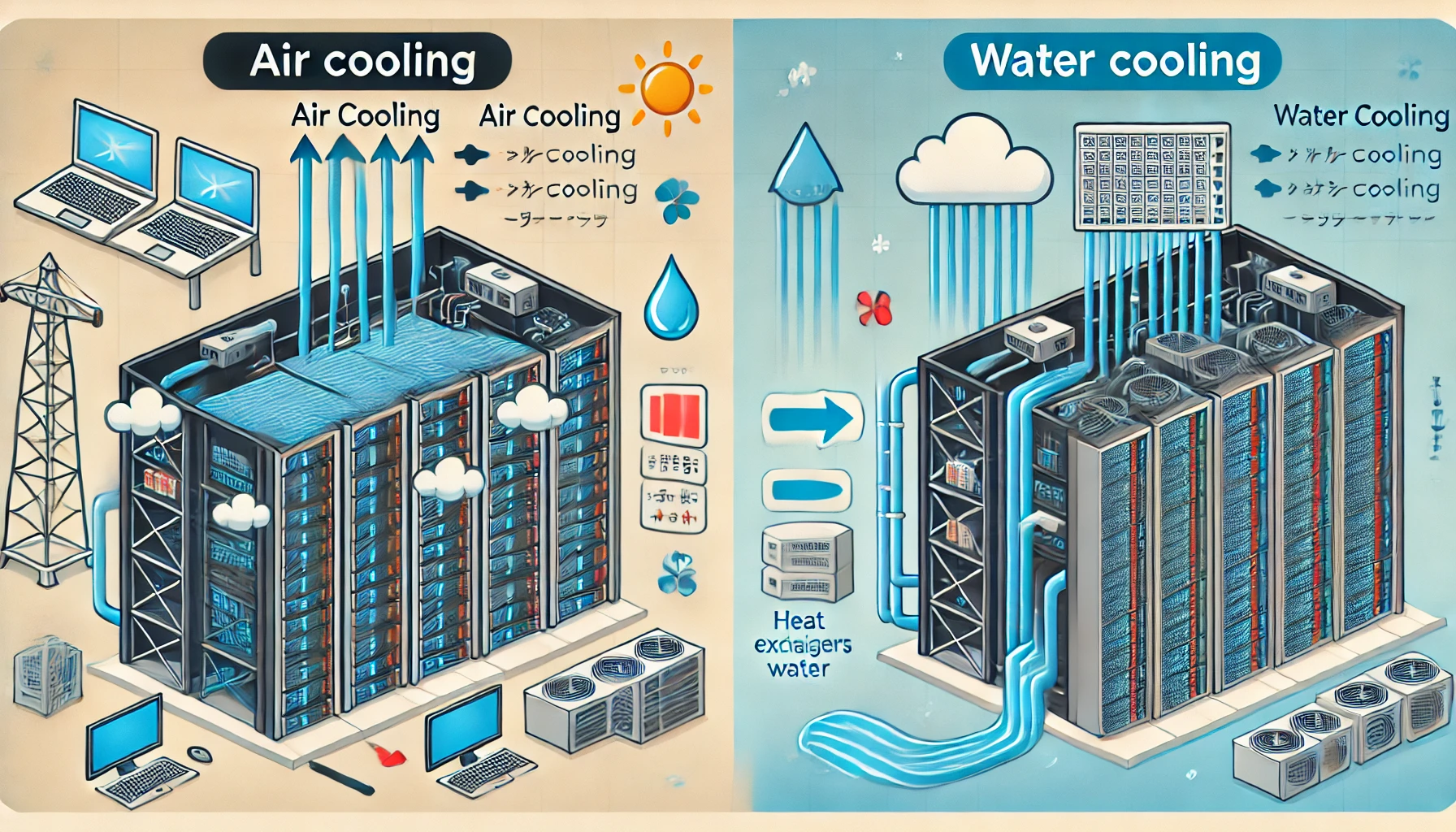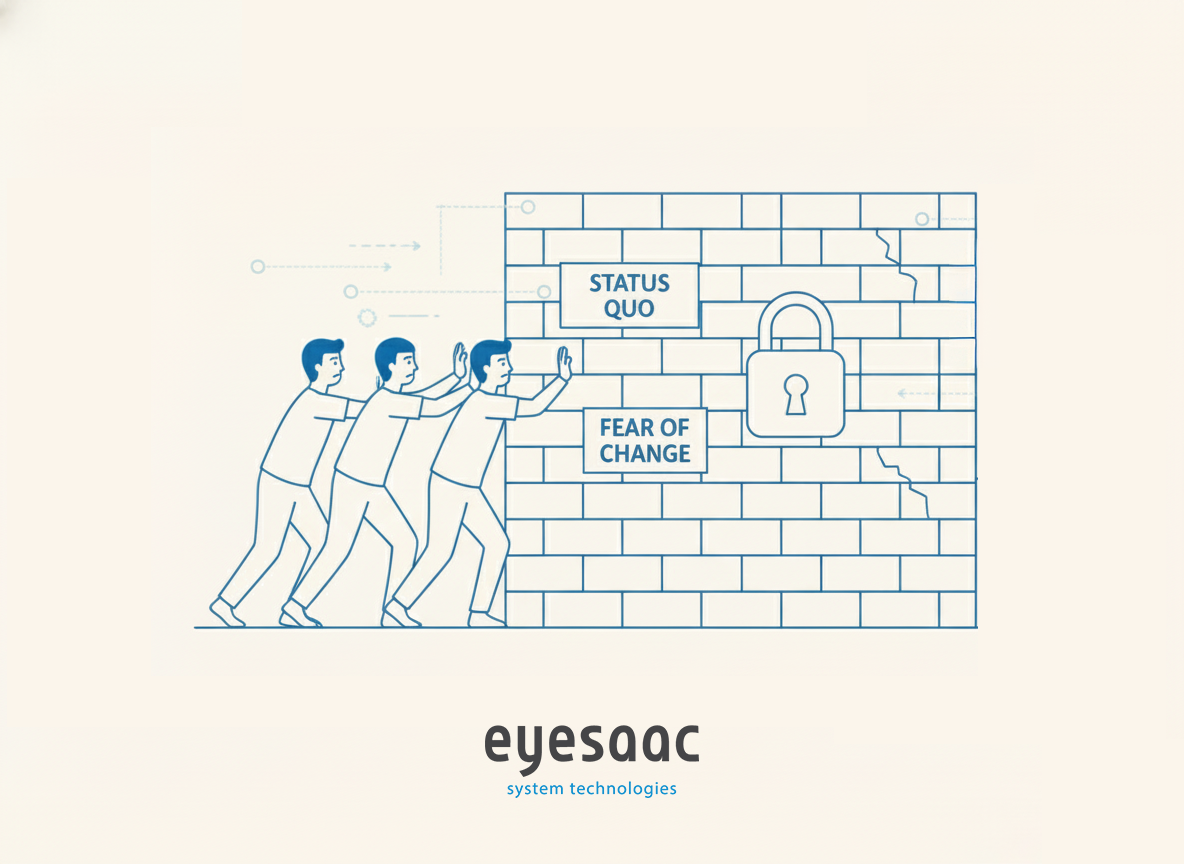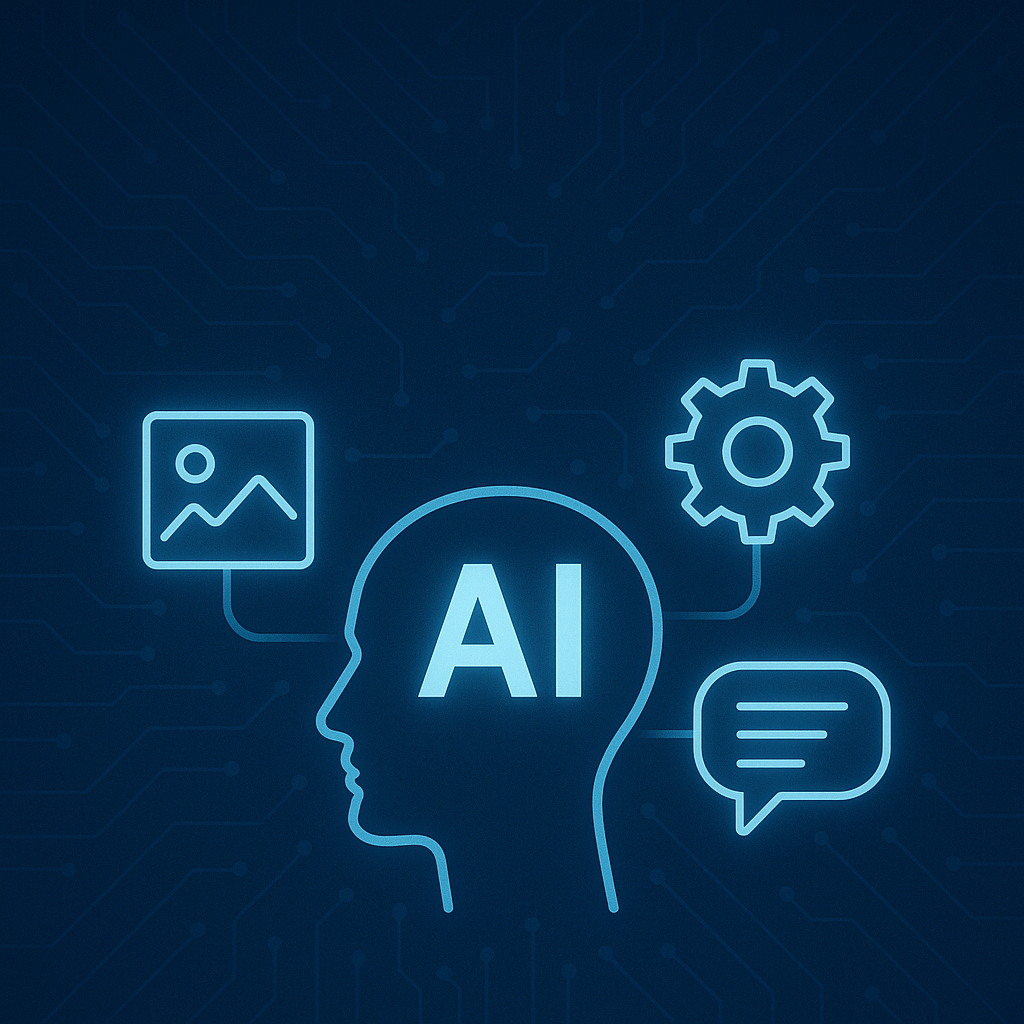― プロが教える、賢い活用術 ―
「エンジニアがいなくてもアプリが作れる」。
そんなキャッチコピーとともに、ノーコード/ローコードツール(以下NCLC)は急速に普及しました。
しかし、現場で導入を進めた多くの企業が直面しているのは、“思ったより使いこなせない現実”です。
最初は便利でも、システムが複雑化するにつれ、保守や拡張に限界が見えてくる。
Eyesaacは、ノーコードの本質を「民主化のツール」ではなく、“設計思考を可視化する実験装置”として捉えています。
① 「誰でも作れる」は幻想である
Gartnerの2024年調査によると、NCLCを導入した企業のうち約65%が1年以内に開発停滞を経験しています。
理由はシンプル。
「誰でも作れる」は、“誰でも設計できる”とは違うからです。
ツールを操作できても、業務ロジック・データ設計・運用フローを理解していなければ、結果は場当たり的になります。
つまり、ノーコードとは“技術の壁を下げる”ものであって、“思考の壁を取り除く”ものではないのです。
② 最大のリスクは「属人化」
NCLCの導入初期は、個人が自由にアプリを作れるため、スピード感があります。
しかし、その自由度が裏目に出ると、「誰が作ったか分からないブラックボックス」が社内に乱立します。
Forresterはこれを“Shadow IT 2.0”と呼び、ガバナンスを伴わない開発が将来的なシステム負債になると警告しています。
便利さの裏には、設計思想の欠如という見えないコストが潜んでいます。
③ NCLCの本質は「試作と共創」にある
ノーコードの真価は、「最終製品を作ること」ではなく「考えを形にすること」にあります。
開発部門と業務部門が同じ画面を見ながら、“どんな仕組みが必要か”を議論できる共創のプラットフォーム。
Eyesaacは、ノーコードを“プロトタイプ思考の促進装置”と位置づけ、
要件定義の初期段階で活用することを推奨しています。
本番システムはエンジニアリングに任せる一方で、
「アイデアのスピード検証」には最も効果的な道具なのです。
④ 賢い活用術 ― 「No → Low → Pro」戦略
ノーコードを“入口”として活用し、徐々にローコード・本格開発へと移行する。
この段階的戦略をEyesaacでは「No → Low → Pro」と呼びます。
1️⃣ ノーコードで業務要件を可視化
2️⃣ ローコードでデータ連携・ルール化を設計
3️⃣ プロ開発で統合基盤に昇華
このプロセスを踏むことで、スピードと拡張性を両立できます。
ツールではなく、移行の設計こそが成功要因です。
まとめ ― Eyesaacの視点
ノーコード/ローコードの本質は“自立”ではなく“共創”です。
ツールが人を解放するのではなく、人がツールの可能性を引き出す。
AIや自動化が進む中で、重要なのは「誰が作るか」よりも「どう設計するか」。
Eyesaacは、ノーコードを単なる省力化手段としてではなく、
組織の思考を可視化し、再設計するための知的装置として企業変革を支援しています。
引用元・参考文献
- Gartner (2024): State of Low-Code Development Platforms
- Forrester (2024): Shadow IT 2.0: The Risks of Citizen Development
- Harvard Business Review (2024): Design Thinking in the Age of No-Code
- Eyesaac Consulting Projects (2023–2025)