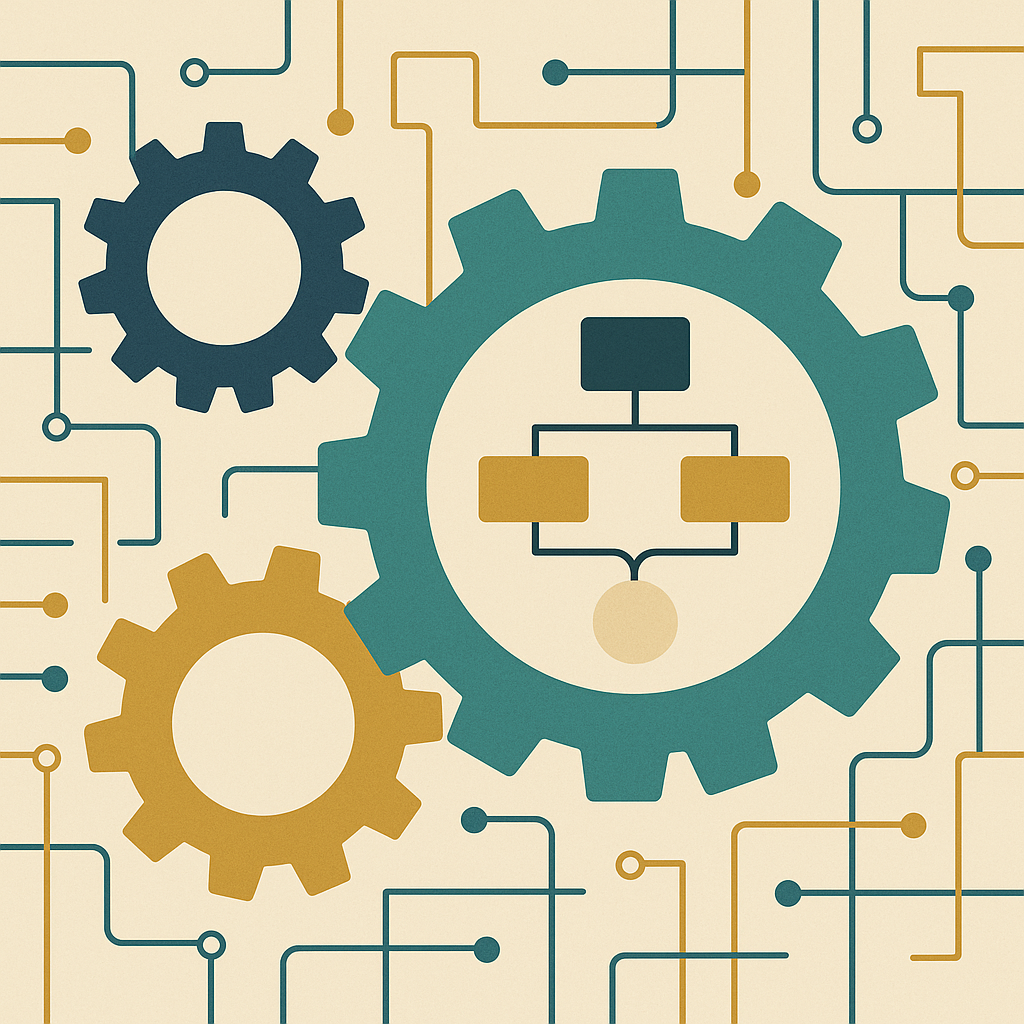― あなたの会社のインフラは本当に「未来」に対応できているか? ―
クラウド化は、もはや選択肢ではなく前提です。
しかし、Eyesaacが企業支援の現場で見てきたのは、「クラウドに移した」ことがゴールになっている企業の多さです。
オンプレからAWSやAzureに移行して満足してしまい、設計思想が“クラウド以前”のまま――。
それでは、真のクラウドネイティブとは言えません。
本当の問いは、「自社のインフラは、変化する未来に対応できる構造になっているか?」なのです。
① クラウド“移行”とクラウド“ネイティブ”の決定的な違い
クラウド移行(Cloud Migration)は、物理サーバーをクラウドに載せ替える行為。
一方でクラウドネイティブ(Cloud Native)は、クラウドの特性を最大限に活かした設計思想です。
たとえば、スケーラビリティ・マイクロサービス・API連携・自動デプロイなど、
変化する需要に合わせて柔軟に構成を変えられる仕組みを指します。
Gartnerの2024年調査では、クラウドネイティブ化を完了した企業のROIは、単純移行型の2.3倍に達していると報告されています。
つまり、クラウドネイティブとは「柔軟性そのものを設計する経営戦略」なのです。
② “インフラの硬直化”が企業成長を止める
クラウドに移行したにもかかわらず、「環境変更に数週間」「デプロイに承認10ステップ」といった状況が残っている企業は多い。
これは、旧来の統制思想をそのままクラウドに持ち込んでいるためです。
本来クラウドは“自由に試すための環境”ですが、ガバナンス重視が過剰になると「仮想的レガシー」を生み出します。
この状態では、AI導入やデータ分析といった次のステップも遅れがちになります。
柔軟に動けないインフラは、もはや「資産」ではなく「固定費」です。
③ クラウドネイティブ化の核心 ― 「構成の自動化」と「観測性」
クラウドネイティブの本質は、Infrastructure as Code(IaC)とObservability(可観測性)にあります。
前者はインフラ構成をコードで管理し、誰でも再現・修正できる状態を作ること。
後者は、システム全体の状態をリアルタイムで把握し、問題を事前に察知できるようにすること。
この2つを組み合わせることで、システムは“生きた有機体”のように自己最適化する仕組みへと進化します。
Eyesaacは、これを「進化するインフラストラクチャ」と定義しています。
④ 経営層が今すぐ考えるべき3つの問い
1️⃣ 自社のインフラは変化に強い構造を持っているか?
2️⃣ システム変更が事業スピードの制約になっていないか?
3️⃣ クラウド投資が運用コストではなく経営機能として働いているか?
これらの問いに“はい”と答えられない場合、クラウドは単なる「環境」になっている可能性があります。
クラウドネイティブとは、経営とインフラを接続する思考法なのです。
まとめ ― Eyesaacの視点
クラウドネイティブとは、技術ではなく変化を内包する経営哲学です。
組織が市場の変化に素早く反応し、インフラが自ら最適化する。
この“動的な経営基盤”を実現することが、真のデジタルトランスフォーメーションです。
Eyesaacは、クラウドネイティブを単なるIT化ではなく、「柔軟性を資産化する戦略」として企業変革を支援しています。
未来に適応する企業とは、変化を恐れず構造を再設計できる企業です。
引用元・参考文献
- Gartner (2024): Cloud-Native Maturity Model and ROI Benchmark
- CNCF (2024): State of Cloud Native Development Report
- AWS Reinvent Keynote (2024): Evolving from Migration to Modernization
- Eyesaac Infrastructure Strategy Reports (2023–2025)