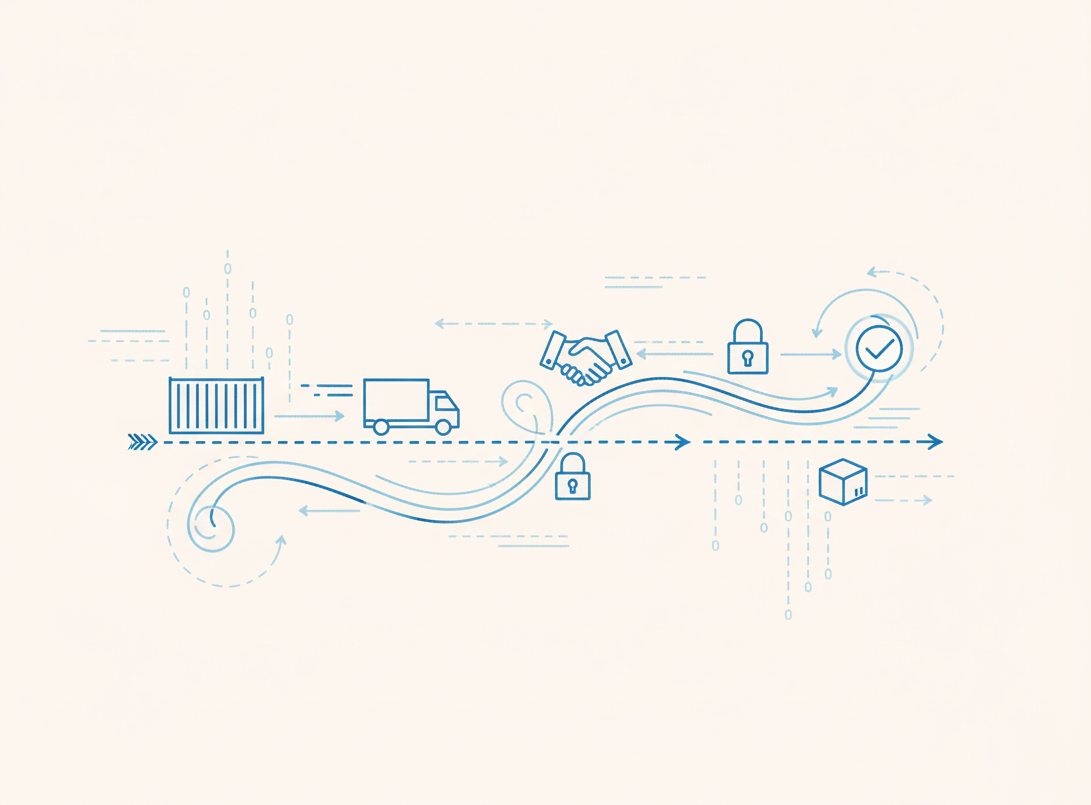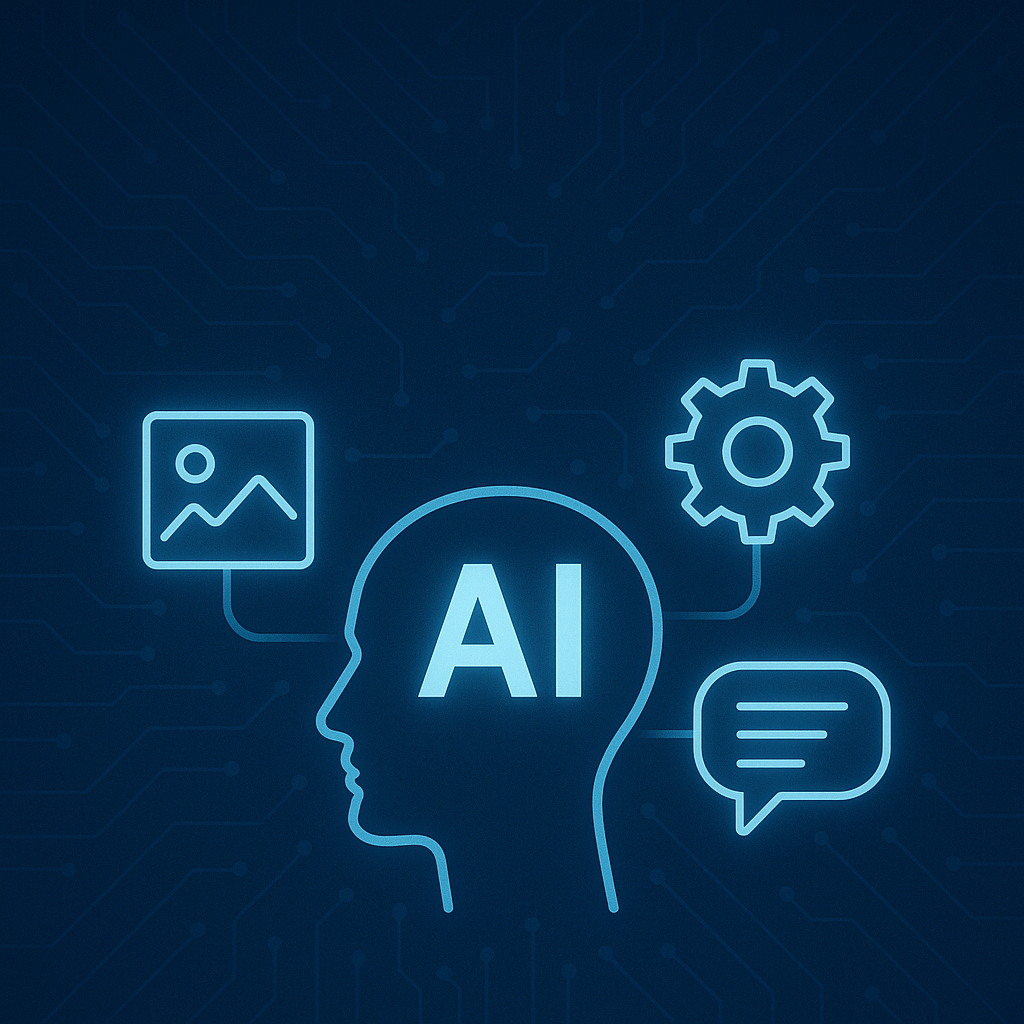― PoCを事業化に繋げる唯一の方法 ―
「PoCまでは成功したのに、その先が続かない」。
多くの企業で耳にするこの言葉は、日本のDX推進の“構造的な壁”を象徴しています。
数百万円単位のPoC(概念実証)が量産される一方で、実際に事業化・定着化するプロジェクトはごく一部。
Eyesaacはこの現象を、“PoC貧乏”=検証に満足して学習を止めてしまう状態と呼びます。
では、なぜ多くの企業がこの罠に陥るのか――そしてどうすれば抜け出せるのか。
① 「PoCの目的」が曖昧なまま始まっている
IDC Japanの2024年レポートによると、日本企業のDX関連PoCの約70%が「明確なKPIを持たずに開始」されています。
つまり、「技術を試す」こと自体が目的化しているのです。
その結果、PoC終了後に次の判断軸――「どの条件で事業化するか」が存在せず、成果が“議論のネタ”で終わってしまう。
PoCは技術のテストではなく、“ビジネス仮説の検証”である。
この原則を共有できていない組織ほど、検証の数だけ疲弊していきます。
② 現場と経営の「距離」が成果を分断する
Gartnerの2024年DX調査では、成功したDX案件の特徴として「現場主導ではなく経営戦略主導」が挙げられています。
日本企業では、PoCが“情報システム部門の実験”で完結してしまうケースが多く、
経営層がそのROIや顧客価値への影響を評価できないまま終わる。
この分断こそ、DXが進まない最大の要因です。
技術導入を経営目線で翻訳する“ビジネスデザイナー”の不在が、PoC貧乏を生み出しています。
③ PoCの終わりは「始まり」である
Eyesaacが実務で支援したプロジェクトでは、PoC終了後に必ず「3段階の検証フェーズ」を設けています。
1️⃣ 技術実証:技術が動くか?
2️⃣ 業務適応:現場に適用できるか?
3️⃣ 経営効果:収益・顧客価値に結びつくか?
多くの企業は①で止まりますが、本質は③のフェーズにこそある。
PoCの次に“事業価値仮説”を設定し、それをKPI化できるかどうかが分岐点になります。
④ 事業化につなげる唯一の方法 ― 「PoV型アプローチ」
PoC(Proof of Concept)ではなく、PoV(Proof of Value)――価値検証に切り替えること。
この考え方は、欧米のDX先進企業ではすでに主流です。
技術が動くかではなく、それが事業にとって意味があるかを最初に設計する。
Eyesaacでは、DXの検証段階から「どの数値が動けば経営効果があるか」を逆算してロードマップを描きます。
その結果、PoCが“通過点”ではなく“事業設計の起点”に変わるのです。
まとめ ― Eyesaacの視点
DXが進まないのは技術のせいではなく、思考のフレームの欠如です。
「技術導入」ではなく「価値創造の仮説検証」としてPoCを位置づける。
この発想転換こそ、PoC貧乏を脱する唯一の方法です。
Eyesaacは、AIやデータ技術を単なる実験に終わらせず、
“検証”を“戦略化”する力で企業のDXを実装型に進化させていきます。
引用元・参考文献
- IDC Japan (2024): Japan Digital Transformation Survey
- Gartner (2024): Critical Success Factors in DX Projects
- MIT Sloan Management Review (2024): From Proof of Concept to Proof of Value
- Eyesaac Consulting Projects (2023–2025)